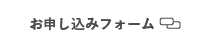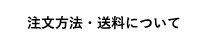国際協力と開発教育
概要
- 田中治彦著
- 発行:明石書店
- 2008.7、A4判、224頁
- 価格:¥2,000(税込¥2,200)
- 出版社サイトを開く
- Amazonサイトを開く
もくじ
「援助」の近未来を探る
元DEAR代表理事(2002~08年)の著者が、日本の国際協力の歩みと開発教育の足取りをまとめた一冊。「援助するということ」「援助と開発の歴史」「PRAとは」「開発プロジェクトのタイプ」「参加型開発とは何か」「日本のNGOと参加型開発」「日本の開発教育」「総合学習とESD」「参加型学習の系譜」「自分・地域・世界をつなぐ学び」「これからの国際協力と開発教育」の全10章からなる。
序章 「援助」するということ
一枚の看板
「援助」する前に考えよう
スポイルとジェラシー
第1章 援助と開発の歴史――タイを中心に
タイのNGO活動の歴史――慈善型開発に始まる
NGOの発展――技術移転型の時代
北タイにおけるNGO活動の発展
参加型開発の模索
HIV/エイズとNGO
エイズ教育と参加型学習
チャチャワンの回想
第2章 PRA――参加型農村調査法とは?
ロールプレイ「バーン村再訪」
村落調査の問題点
PRAの内容
従来の「開発観」の転換
第3章 開発プロジェクトのタイプ
慈善型プロジェクト=ニュー・ライフ・センター
技術移転型プロジェクト=山地農業研修センター
参加型開発=土地利用図づくり
「居場所」の提供=エンパワー財団
参加型学習=ピン川環境保全協力協会
タイのNGOの課題
第4章 参加型開発とは何か?
ハートの「参加のはしご」
主体的な参加の状態
参加型開発における「はしご」
主体的な参加への「転換」
プロジェクトの連続性・参加の不連続性
第5章 日本のNGOと参加型開発
シャプラニールの誕生=慈善型援助の時代
本格的な国際協力への模索
ショミティ方式の発展
ショミティ方式の行き詰まり
参加型開発の模索
見えにくいプロジェクト
NGOの説明責任
第6章 日本の開発教育――開発問題をいかに伝えたか
開発教育の始まり
『たみちゃんシリーズ』『地球の仲間たち』
注目される開発教育
「貧困の悪循環」「援助と開発」
開発教育の地域展開と参加型学習
人権教育と開発教育教材
地球的課題と開発教育
第7章 総合学習とESD(持続可能な開発のための教育)
「総合的な学習の時間」
開発教育のカリキュラムと教材
学校・地域・NGOの連携
九・一一事件と開発教育
持続可能な開発のための教育(ESD)
環境教育とESD
開発教育とESD
ESDの教材
第8章 参加型学習の系譜
参加型学習の起源――グループワーク
学習のコペルニクス的転換――ジョン・デューイ
日本における「新教育」
青年団と共同学習
パウロ・フレイレと識字教育
ローマ・クラブと『限界なき学習』
第9章 自分・地域・世界をつなぐ学び
アクション・リサーチと子どもの参加
池袋西口アクション・リサーチ
新しい環境学習・地域学習
PLAとアクション・リサーチ
参加型学習による日本とタイの交流
グローバル化にさらされるタイの農村
地域づくりと参加型学習
終章 これからの国際協力と開発教育
「アイ子」はどうしたらよいのか?
援助・国際協力の行方
国際協力をめざすには
開発教育と参加型学習
参加型学習の「虹」
あとがき
参考文献
国際協力・開発教育年表
国際協力・開発教育用語集
ご注文方法
- DEARまでウェブ、ファクス、お電話にて直接ご注文ください。 詳しくはこちらのページをご参照ください。
- DEAR事務所(東京都文京区)で直接ご購入いただくことも可能です。来所の際は事前にご連絡ください。